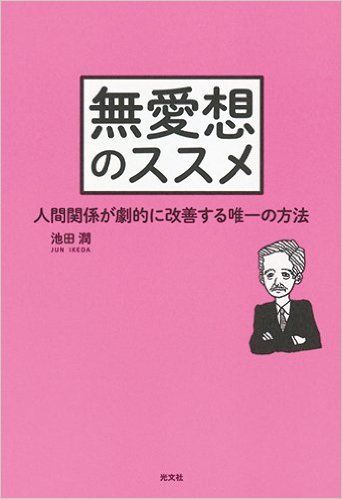「愛想笑い」で人生は好転しない。もっと無愛想でいいんじゃない?
「愛想が良い人」は人付き合いがうまく、誰にでも好かれる印象があります。でも実際には誰にも嫌われないように生きているため、次第に自分を見失ってしまい、誰にも大切にされなくなってしまう傾向があるのです。
ここでは、池田潤氏の著書『無愛想のススメ 人間関係が劇的に改善する唯一の方法』より、どうすれば「愛想が良い人」をやめられるのか、見ていきましょう。
「第一印象」は
悪いほうがいい

「第一印象が大事!」と、よく聞くと思う。なぜなら、一度相手に与えた印象はなかなか覆すことが難しいからだ。しかしここではあえてその主張に「ノー」と言ってみよう。もちろん、何も意識せず自然と印象が良くなることはOKだ。しかし、必要以上に良くしようとしたり背伸びをしても意味がないばかりか、かえって悪影響を与えることになってしまうのだ。
なぜなら、第一印象で与えた良いイメージを少しでも壊してしまったら、一気に評価が下がってしまうからだ。それは第一印象が良ければ良いほど下がり方は大きくなる。逆に第一印象が悪い人は、そもそも期待されないので、それ以上評価が下がることはない。むしろ少しでも良い印象を与えれば大きく評価されるのだ。
「無愛想に生きる」とは、自然体で生きるということだ。無愛想な人はそもそも第一印象を良くしようなどとは思わないため、「自分はこんな人間です」と地を晒してしまう。相手に良い印象を与えることよりも、自分自身でいることを大事にするのだ。
愛想笑いは
「不感症」を生む
よく「いつも笑顔でいましょう」と言われることがある。確かにいつも笑顔でいられたら素晴らしいし、そんな社会になればいいと思う。しかし、生きていればつらいことも悲しいこともあるのが現実だ。
いつも笑顔でいるためには、怒りや悲しみ、寂しさといった「ネガティブ」な感情を無視するようになる。すると、どんどん感情を感じることができなくなり「不感症」になっていく。
怒ってもいい。泣いてもいい。寂しくてもいい。つらいと思ってもいい。それらはすべて人間としての自然な感情だ。そこに罪悪感を感じる必要などないのだ。
いつも笑顔じゃなくてもいい、と言われて初めて人は心の底から笑うことができる。愛想良く笑っている必要などない。無愛想でいてもいいのだ。そう許可したときにこそ、本当に笑うことができるのだ。
悲しみを否定した
「笑顔」は美しくない
ここでは無愛想を勧めてはいるが、つねに無愛想でいるべきだと言っているわけではない。大切なのは無愛想に「なれる」ことだ。社会で生きていくにあたって、愛想良くしなくてはいけないときもある。ただ、無愛想に「なれる」ことは生きていく上で非常に大事なことだし、無愛想になれる人は「なれない人」に比べて、日々の精神的ストレスもずっと少ない。
無愛想になれない人は、嫌なことをされているにも関わらず笑顔でいる。面白くないのに笑っている。そうやって我慢して自分を犠牲にしてつらいことに耐えていれば、いずれ人生は好転するのだろうか?
この社会では、悲しみを表現することが許されていない。悲しみや寂しさは恥ずかしい感情であり、抑えつけなくてはいけないものだとされているからだ。悲しみを表現させないから、悲しませるようなことをしている人たちは、いつまで経っても自分がしていることの重みに気がつかない。
人間の感情と本気で向き合わせないから、人のことに無関心だったり、人の気持ちを感じられない人間が増えていくのだ。
悲しみや寂しさを受け入れた上での笑顔。それが本当に美しい笑顔なのではないだろうか。
人間関係は
「無愛想」でうまくいく

対人関係で、愛想良く振る舞っていてもなかなか相手との仲が深まらない、どこか遠慮したままでぎこちない感じになってしまう。そんな経験はないだろうか?相手との仲を深めたいなら、愛想良くするのではなく、無愛想にズケズケとしてしまえばいいのだ。
想像してみてほしい。親友に愛想良くしている人はいない。人は親友にならズケズケと物を言うことができるし、遊びに誘われても「疲れてるから無理」と言えるし、帰りたくなったら「今日は帰るわ」と言える。
ただ、愛想笑いする人も本当は心の奥底で人と繋がりたいと思っている。しかし、怖い。だから一定の距離をとって愛想笑いをしてしまうのだ。これは恋愛でも同じことだ。恋愛で悩む男性はいつも女性にニコニコしているが、どう頑張っても友達止まり。心の深い部分で繋がることはできないし、自信がないことがバレバレ。そんな人と一緒にいても楽しくないのだ。
無愛想になれる人は、人間関係でもかなり早い段階からズケズケしている。ズケズケしていることによって心の距離が縮まり、相手に信頼され、最初から心を開いた関係を築くことができる。
愛想笑いをしている間は、親友にも恋人にもなれないのだ。