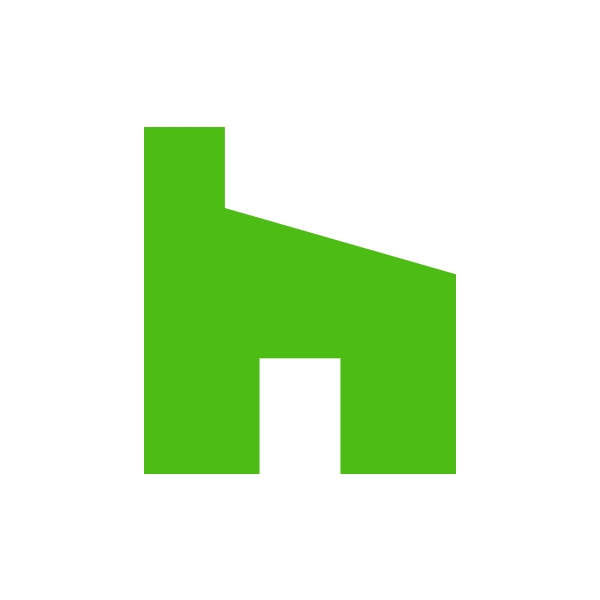【Vol.1】ロシア人は、夏のバカンスを「ダーチャ」で過ごす
夏になるとロシア人は、田園地帯の小さな別荘「ダーチャ」で家族や友人とともに週末を過ごす。
18世紀に貴族の間で広まった田舎のセカンドハウスは、ロシアの建築と文化において特徴的な存在であり、今もその人気は衰えていない。ロシアのセカンドハウス事情は、ピョートル大帝の時代からどんなふうに変化してきたのだろうか?
貴族がゆったり過ごす
田舎の小さな別荘

ロシア帝国の皇后アレクサンドラ・フョードロヴナが夏を過ごすダーチャがあったのは、サンクトペテルブルク近郊の町ペテルゴフ。1829年に建てられ、ポーチの柱が樺の木の幹のようなデザインになっている。
ダーチャとは、特定の建築様式のことではなく、どちらかといえば生活様式を指す言葉。ロシアにダーチャが初めて登場したのは、ピョートル大帝(1672-1725)が統治していた時代だ。
18世紀当時、ダーチャ(「与える」という意味のロシア語の動詞дать<ダーチ>に由来)とは、宮廷人が堅苦しい生活を抜け出し、田舎でガーデニングや菜園づくりをしながらゆったり過ごすための、当時としては小規模な住まいのこと。つまり当初のダーチャは、すでに豪華な屋敷を所有している人たちの別荘だった。

写真は、1727年にペテルゴフの町につくられ、1843年に建て直された、通称「海辺のダーチャ」。女帝エリザヴェータ・ペトロヴナがひっそりと過ごすために作られたプライベートな屋敷で、誰も約束なしに訪れることはできない場所だった。石造りの2階建ての建物に、木製の棟が1つ、そして近くには付属の農場もあった。
19世紀半ばになると、ロシア貴族たちはみな、このようなダーチャを手に入れたがるようになった。しかし全員に行きわたるだけの建物も区画もなかったため、賃貸ブームの始まりとなる。代々受け継がれた屋敷や庭園の持ち主は、敷地内にある小さな建物を貸し出すようになった。
田舎暮らしに必要なものが一通り揃っている場合もあれば、空っぽなこともあった。何もない場合は、入居する家族が自分たちの家具や食器類、寝具などを持って来た。
独立した家屋だけでなく、広い屋敷の中の使っていない棟が貸し出されることもあった。その場合、屋敷に住み続けている持ち主は、ふだんのしきたり通りに、コルセットを締めたドレスといった正装で朝食に登場するのが常。
一方、借り手側にはそれほど厳しい作法は求められなかったようだ。そして現在でも、ロシアでダーチャと言えば、建物のタイプではなく田舎暮らしを意味するものとなっている。

プライベートで気の置けないライフスタイルというのが、今でもダーチャ生活の特徴。小さなアパートメントに住む現代のロシア国民は、郊外にも小さなダーチャを持っていることが多い。
田舎に家を所有している人なら、さらに人里離れたところにもう1軒家を建て、そこで「普段の生活」ではできないような暮らしをする、というのが定番だ。鉱山労働者がキュウリを育てるその隣では、政治家がジャガイモを荒らす害虫と戦っている……なんて光景は、ダーチャでしか見られないもの。

サンクトペテルブルク近郊のコマロヴォにある木造のダーチャ。20世紀初頭にアールヌーヴォー様式で建てられた。
自然と触れ合う
ダーチャの季節

1892年につくられた、アーティストのアレクサンドル・ベノワ一家のダーチャ。
ロシアの季節はふたつ、「冬」と「ダーチャ」だ。
ダーチャの習慣が始まった当初から、春に移り住んで秋の終わりまで滞在するのが一般的だった。著名なロシア人画家で美術史学者のアレクサンドル・ベノワ(1870-1960)は、家族とのダーチャ生活を振り返り「まだ寒くて雨の多い季節でも、できるだけ早くサンクトペテルブルクを抜け出してダーチャで暮らしたかった」と述べている。
当時の貴族たちは夏の別荘に来ると、庭園で長い散歩をしたり、ピクニックをしたり、ボート、体操、サイクリングなど、19世紀の都会ではできなかったさまざまな遊びを楽しんでいた。
これには、当時のヨーロッパで「自然」がトレンドとなっていたことも影響している。例えば、フランスでは印象派の画家たちが自然の中に出かけて絵筆を取り、イギリスではヴィクトリア女王の統治下で自然の景観を模した庭園やピクニックが流行した。

20世紀初めのロシアで田園生活を楽しむ一家。
有名なロシアの作家、アントン・パブロビッチ・チェーホフの1898年の小説に『新しい別荘』という短編がある。ロシアの学生なら必ず知っている作品だ。その中で、ダーチャの暮らしが次のように描かれている。
「畑を耕したり種を蒔いたりするためではなく、ただ喜びを感じ、新鮮な空気を吸って生活するのだ」


こちらのテラス付きダーチャは、1930年代から50年代に建てられたダーチャによく見られるタイプ。
ダーチャは、太陽が降り注ぐ夏の気候をふまえてデザインされている。昔から人々がダーチャに滞在するのは温かい時期だけだったため、建築にもそれが反映されているのだ。
ステンドグラスの窓を使った明るいテラス、彫刻を施したバルコニーやメザニンは、厳しい冬に適した仕様とは言えないが、ロマンチックなムードを演出し、自然を近くに感じさせてくれる。
ガラス張りのフロントポーチやベランダは、日中に温まるように家の南側に配置するのが一般的だった。田舎暮らしの日々の生活では、ここがリビングルームやダイニングルーム、書斎になることが多かったようで、ときには寝室になることもあった。

モスクワ近郊、ノヴォ・ペレデルキノ地域にあるネオロシア様式のダーチャ。20世紀初頭、建築家のヒョードル・シェーフテリが設計した。

ソビエト時代になると、ダーチャは政治家や特権階級のものとなった。1917年のロシア革命後、ダーチャはほぼすべて国有化されてしまったが、革命以前のライフスタイルが否定されるなかでも、ダーチャ文化が消え去ることはなかった。しかしダーチャの姿は大きく変化し、厳しい規制が加えられるようになる。
例えば、1938年に出された『政府職員のダーチャについて』という決議では、家族世帯の職員のダーチャは8部屋まで(キッチンとリビングも含む)と制限された。
1930年代から50年代にかけて、ダーチャを持つことができるのは、政府職員や著述家、学者など、その権利を与えられた特権階級だけで、人々のあこがれの的。ダーチャは国有の場合も、個人で所有している場合もあったようだ。

『ドクトル・ジバゴ』の著者で詩人のボリス・パステルナークが暮らした1930年代のダーチャ。モスクワ近郊、ペレデルキノ。
作家組合や建築家組合といった団体は、自分たち専用の夏の集落を作っていた。そこでは、近所に暮らす人はみんな同じ職業ということになる。これに似たかたちで、ソビエト時代の企業も土地区画を労働者に与え、同じ職場や工場で働く人たちが近所同士に暮らすダーチャができるようになった。
モスクワ近郊でもっとも有名な夏季別荘地といえば、ペレデルキノだ。ここにはノーベル賞受賞作家である詩人のボリス・パステルナーク(1890-1960)のダーチャがほぼ当時のままに残っている。この村で初期に作られたダーチャはドイツのデザインを用いており、ヨーロッパのコテージ風の趣きがある。

ダーチャはまた、自己修練の場所でもあった。
新しい時代のダーチャは、帝国時代の豪華な別荘とはまったくの別もの。軍の高官のダーチャでさえ、普通の小さな家で、特別な設備があるわけではなかった。ソビエト時代の典型的な1区画の広さは600平方メートルで、この数字(ロシア語でシェスト・ソトク)が、そのままソビエト後期のダーチャの呼び名として定着した。
郊外地域組合の規則によって、木をどこに何本植えてよいかから、認められる家の大きさまで、細かく指定されていた。例えば3人家族の場合、寝室は1つだけで、リンゴの木を植えるなら6本以下と決められ、面積の規定は頻繁に変更されたが、土地も家自体も決して大きいものではなかったようだ。
例えば1960年代から70年代には、600平方メートルの区画の場合、建てることのできる家の大きさは25平方メートル以下。1980年代には、600~1000平方メートルの区画の場合、家の大きさは50平方メートル以下とされていた。
バレリーナのマイヤ・プリセツカヤ(1925-2015)は、家族で過ごしたザゴリャンカ村の共同組合ダーチャについて、下見板張りの2部屋しかない家だったが、一家にとって「王様のような贅沢」だったと述べている。
たいていどの家でも、バスルーム(トイレと洗面台)があるのは、母屋の脇に建てた下見板張りの小屋の中だった。ダーチャの住人たちにとって、日常生活の不便は大した問題ではなかったようだ。

ダーチャは狭かったため、キッチンは別の建物か屋外に作られることが多かった。そのため現在でも、アウトドアキッチンを設けるのがダーチャの定番になっている。こちらの夏用アウトドアキッチンは、2013年に〈ブロ・アキモフ&トポロフ〉が手掛けたもの。

こちらの小さなダーチャは1960年代にオーナーが手作りで建てた。

ダーチャは、食料を育てる場所にもなった。
ニキータ・フルシチョフがソ連の指導者となったころ(1955-64)から、食料不足に対応するため、ロシアの人々はダーチャで自分たちの食べ物を生産するように。
食料問題への対応に伴い、ダーチャは、週末に車に荷物をたくさん積んで田舎に向かい、畑の世話をして、夕方には採れた果物をジャムにする…という生活を意味するものになった。
ソ連国民は揃って「週末農家」となったのだ。農作業は週末まで待てないこともあるため、距離が許せば、平日でも仕事のあとでダーチャへ行って作業することもあったという。