10年間、友達なのにセックスしてた
あかりとはじめてセックスをしたのは、中学校を卒業した日。
物心ついたときから、お互いの家を行き来していた幼なじみ。小さいころは一緒にお風呂も入っていたし、家族ぐるみで仲が良くて、もうほとんどキョウダイのような存在だった。
「…なんか変な感じ、ずっと一緒に登校してたのに、もう同じ学校に通えないんだね」
卒業式を終えて一緒に帰り、そのまま僕の部屋にきた彼女はベッドに寝転びながらそう呟く。
「…なにお前、さみしいの?(笑)」
「べつに。むしろ、お前ら付き合ってる〜って冷やかされる人生から解放されると思うと清々しい」
多分あの瞬間、僕たちのなかにあったのは小さな苛立ちと、開放感と、もの哀しさで。
卒業と同時に生まれた虚無感を、ぴったりと埋めあわせられる相手が、隣にいることをわかっていた。
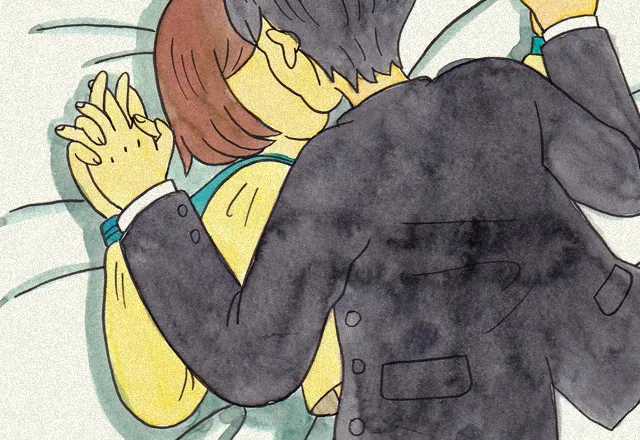
──下手くそなセックスだったと思う。僕はそれが初めてだったし、きっと彼女にとってもそうだった。
でも気持ちがよかったことだけは、鮮明に覚えている。
誰よりも自分を理解している、口に出さない感情まで共有できる相手とのセックスは、僕らを体で結びつける関係に塗り替えるには容易かった。
思春期の僕らにとっては、あまりにも。
ただの幼なじみからセフレになって、
僕らの関係は25歳になるまでつづいた
僕らは心の中に生まれる虚無を、埋めあいつづけられる唯一の存在だった。家族も親友も誰も知らない、口に出したことすらない体の奥の深い欲求まで、手に取るようにわかってくれる。
カラダの相性だけじゃ足りない。記憶にないほど昔から一緒に生きてきた僕らの相性は、すべてが、パーフェクトだった。だから10年もつづいたんだ。もう今更、離れられるはずもなかった。
25歳になった僕らにはそれぞれ恋人がいて、金曜日の夜から土曜日の昼までは恋人と過ごす時間。それが終わったら、土曜日の夕方から合流するのがルーティーン。
我ながら、最低だと思う。
恋人を抱いて、「好きだ」なんて散々愛情を振りまいたあとに、平気な顔してあかりを抱いている。この10年の間に、僕もあかりも恋人がいることは何度もあった。セフレの存在に気付かれて、別れを切り出されたことも数回ある。
恋人のことが、好きじゃないわけじゃない。大事に思ってないわけでもない。
泣かれれば後悔するし、セフレのせいで振られれば自己嫌悪にもなる。
ただ、それらすべての感情と「あかりとのセックス」を秤にかけたとき、寸分の迷いもなく、後者を選んでしまうだけ。
「離れられない関係」の終着が、
どこにあるのかなんて考えたくもない

その日は雨で、残業つづきの水曜日だった。「疲れてるから」と恋人の誘いを断り、家にあかりを呼び出す。
インターホンが鳴ってドアを開けると、想像どおり無愛想な顔であかりが立っていて「あんたね、雨の日の夜に女の子呼び出さないでよ」と開口一番にクレームを僕にぶつける。
実家を出た後も、僕らはすぐ近くに住んでいた。離れる選択肢を考えたことはない。自然と、そうなった。
「ごめん、あかりとセックスしたくてさー」
「彼女いるのに懲りないね」
「自分だって彼氏いるだろ」
「いるけど」
あかりは勝手に冷蔵庫から缶ビールを出し、蓋を開けながらベッドに腰掛ける。
風呂上がりらしく髪は少しまだ濡れていて、ダボっとしたTシャツにショートパンツを履いていた。肌の露出が多くても、あかりは色気をムンムンとさせるタイプではない。僕と会うときは高確率でスッピンだし、気取った下着をつけてきたりもしない。おまけに貧乳。
それでも僕は、姿を見るたびに何度でも欲情した。抱くようになって、10年経っても。
手元のビールを奪って、あかりが顔を上げきる前に押し倒す。
「ちょっと、まだ飲んでる」
「あとで」
Tシャツを脱がせて、暗い部屋でもわかるくらいに綺麗な白い肌に吸いつく。昔からスポーツ嫌いだったあかりの体に傷はほとんどなく、筋肉もなくて柔らかい。隅々まで撫でるように触っていくうちに、残業で蓄積された疲労感は溶けるように消えていった。
ドキドキはしない、緊張もしない。甘い言葉を吐いたりもしない。愛情だとか執着だとか共依存だとか、そんなものは最初からどうでもよかった。
荒々しく唇をふさいで息を奪って、あかりが腕をのばして僕の体を引き寄せたら、もう余裕がない証拠。その瞬間が、幸福度の頂点だった。
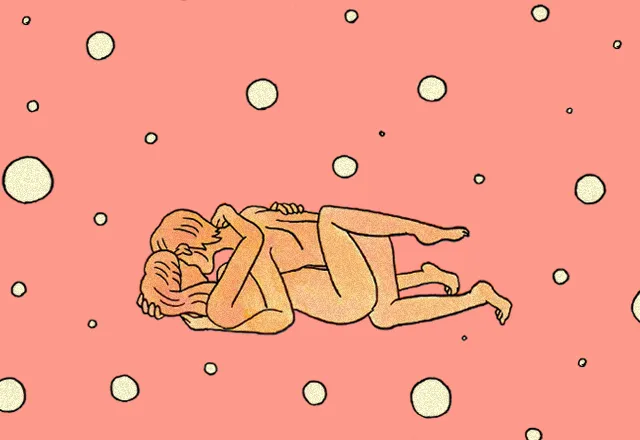
「…わたし結婚するっぽいんだよね」
事情のあと、炭酸の弱くなったビールを飲み干したあかりは、予想もしなかったセリフを口にした。
「……え、まじ!?」
「まじ。こないだプロポーズされた」
「OKしたん?」
「うん」
「お前が結婚…!?まじか……いや、おめでとう!」
ってかそういう報告するなら、もうちょっと顔色変えろよ!淡々としすぎだろ!と心のなかでツッコミながらも、あかりが結婚をしたい相手と結ばれるなら良いことだ。
「声大きいよ(笑)ありがと。……てことで、こーゆうのは今日で最後ね」
………え?
「じゃ、明日も仕事だし帰るから」
「えっ、いやいやちょっと待って……今日で終わりって本気で言ってる?」
「うん」
「なん…、今まで彼氏いても変わらなかったじゃん」
「え…彼氏と旦那は違うでしょ?わたし、不倫なんてしたくないし」
動揺する僕とは正反対に、相変わらずあかりは淡々と言葉を並べて「なんでそんな驚いてるの?」と言わんばかりに首を傾げた。
ちょっと待てよ……なんで?
この関係って、特別だったじゃん。誰にも邪魔できない、唯一無二だったじゃん、僕ら。
「…10年もつづけたのに?」
渦巻く不安と緊張のなかで、やっと絞り出した言葉がこれ。
あぁくそ、なんでこんな重い女みたいなこと言わなきゃいけないんだよ。
「…どういう意味?」
「わかってんだろ、あかりは僕の感情なんてぜんぶ」
「…なにそれ。言わなきゃわかんないよ気持ちなんて」
その言葉を聞いた瞬間、頭を殴られたみたいに視界がグニャリと歪んだ。
嘘だよ、わかりあってたじゃん僕ら。口になんて出さなくても、人生で一番理解しあってたじゃん。恋人なんかより、代わりのきかない存在だっただろ。
「…もう会わないってこと?」
「そうじゃなくて、ただの幼なじみに戻るだけだって」
なんだよこれ。なんでこんなこと言わなきゃいけないんだよ。触れあえない幼なじみに戻るのに、なんであかりはそんな普通なんだよ。
「変わらない関係なんてないよ。あんたもそろそろ、彼女のこと大事にしな?」
放心する僕の横をすり抜けて、「じゃあね」といつもの声色で去っていく。10年間の終止符を打ったとは思えないくらい、彼女は普通だった。
「最初から、いてもいなくてもよかった」と、言われた気がした。
僕はきっと、体を重ねたぶんだけ
「ただのセフレ」になったんだ、君にとって

──それから半年と少し経ったころ、僕のもとに結婚式の招待状が届いた。
家族ぐるみの付き合いだ、気は進まなかったけど欠席できるわけもなく、日に日に大きくなっていった重い虚無感を抱えながら、結婚式の日を迎えた。
久しぶりに顔をあわせた“僕と10年間セフレだった彼女”は、そんな事実を微塵も気づかせない、完璧な純白に包まれていて、幸せそうに微笑んでいる。
最初から、僕の妄想だったようにすら感じる。真っ白なウェディングドレスに、僕らの時間は跡形もなく飲み込まれて消えた。
「あかりは僕の一番だから、僕もあかりの一番だよね」
当然のようにそう思いつづけていた自分が、滑稽で、恥ずかしくて消えてしまいたい。
好きだ、なんて思ったことはない。
彼女になってほしいなんて考えたこともない。
でも他の男と腕を組んで一生の愛を誓ってみせるあかりを見て、「なんで隣にいるのは僕じゃないんだろう」なんて
……クソみたいな思いが押し寄せてきてほんと嫌になるよ。
誰よりも君を抱いたのは、僕だと思う。
そのすべてのセックスが、理想とエゴの押し付けでしかないことを知りながら、君は許してくれていたんだね。
(取材協力:H.Tさん)
TABI LABOでは、みなさんの「マッチングアプリ」体験談を物語にしています。どこかに残しておきたい、マッチング相手との忘れられないできごとがあれば、こちらのフォームに、ペンネームと内容(箇条書きなど簡単なものでも可)をお送りください💌









