「料理なんて、結局おいしければそれでいい」
カルチャー、アート、ミュージック、ファッション、いずれも接頭語につくのはストリート。ではフードはどうだろう。とたんにチャルメラが聴こえてくるような屋台臭がしてくる?でも、それだって単なるイメージの話。
路上の掛け合いから生まれるシーンはどれも、ほとばしるような熱量を感じさせる。そこにしかない空気と、予測不可能な即興性。それがストリートの醍醐味。20席あまりのこのレストランにも、圧倒的なライブ感で人と食をつなげていく料理がある。

決して見た目が派手なわけでも、インスタ映え“しすぎる”わけでもない。なのに素材の持つポテンシャルが縦横無尽に解き放たれ、圧倒的に強く、ときにエロさすら感じてしまう一皿。大脳皮質に直接訴えかけてくるこの感覚は、もはや「官能」に近い。
ウェブや誌面で語り尽くされた挙句、「モダンフレンチ」や「創作フレンチ」などと形容されているけれど、この味を生み出す当事者たちは、ほとんど意に介さない様子でさらりとこう受け流した。
「結局のところ、おいしければそれでいい」と。


例えばこう。生の甘エビに合わせるのは、歯ごたえ残る完熟手前の白桃。これにエスプーマ仕立てのソースをかけて供されるのだけど、聞けばこれ、「カルピス」だという。(ウソでしょ?)ところが、いっぺんに口に入れるとどうだろう。調和が取れていて、しびれるくらいにウマイ。
ピンポイントの組み合わせなのは言わずもがな。メイン食材の甘味に酸味を合わせるといった具合に味覚の足し引きで味の構成を整えている。直感的に「おいしい!」と感じてしまう理屈はそこらしい。
アヴァンギャルドやイノベーティブと言えば聞こえはいいが、こうした理論の構築がビシッと底辺にあり、味覚を分類したうえで紡ぎ出された一皿。奇をてらったり、遊び心だけではこうはいくまい。
ところが、ここでもつくり手はまるで他人事のように話す。

その風貌まるで竹原ピストル。人懐っこい笑顔で、底抜けに明るく、豪胆で、しゃべり出したら止まらない。無骨なように見えて、じつは超実直。シェフ・鳥羽周作という人間味が、そのまま一皿一皿からにじみ出てくる。
9皿(ランチ6皿)構成のコース1本で勝負する『Gris(グリ)』は、ペアリング<つながり>を大切にしながら、シンプルに「おいしい」を追求する。全国各地から集まる想いの詰まった食材を丸ごと受け取り、それを自分たちの最適な方法でお客の待つテーブルまで送り届ける。簡単に言えばこれだけ。
「だから、うちはアツアツのままを提供する」
勝手な解釈だけど、このアツアツには料理の適温という意味のほかに、信頼のおける地方の生産者たちの「ものづくり」にかける熱意も間違いなく内包されている。これこそがGrisの真骨頂だ。


では、店とお客のセッション、この駆け抜けるスピードやライブ感に、僕たちは“ストリート”っぽい何かを覚えてしまうのだろうか。唯一無二の味を創造する料理人に、こう聞いてみた。
──正直、食べてる最中、神経のネジを緩めるヒマさえありませんでした。突拍子もない料理ってよく言われませんか?

鳥羽:よく言われます。だけど、ベースはちゃんと意図があって、そこに対するロジックもある。アプローチもすごく綿密ですし。だから、あの組み合わせでも最短距離でおいしい!って思えるんです。そういう設計を自分たちなりにしてますから。
いくらキレイな皿を作ったって、こういうところが分かってないと何の意味もないですからね。見栄えはいいけど、食べたらおいしくないなんて、どうしようもないじゃないですか。本質をついた料理ってもっとシンプルですよ。おしゃれかどうかより、まずは本質ありき。

「俺は料理そんなに上手くないから」。
聞き間違いかと思うようなひと言に、耳を疑った。が、Grisの料理は総合力で成り立っている、とシェフは得意げに強調する。

鳥羽:カリスマシェフがいて、あとは黙ってただ働くなんてもう昔のやり方。シェフだけが雑誌でて、テレビでて、そんなの広がりなんてなにもないと思う。料理業界って、未だに職人気質なところがあるから、もっとチームで働くとか、一緒に創り出すとか、クリエイター集団的な感覚にしていきたいんですよ。
32歳にして料理界へのキャリアチェンジがどうのこうのよりも、いい意味で料理の本質をきちんと理解している人。エゴや自己満によるものとはまったく異質の、根の張った自信がそこにあった。
このGrisの味をシェフとともに2人の若者が支えている。

有名フレンチレストラン「バカール」、「ジョエル・ロブション」での下積みを経て、2016年よりシェフのサポートを務めるスーシェフ新圖さん。

「入ったばかりで今はすべてが勉強」と、金垣さんは未来を見つめている。
「ヤバくね?」が数分おきに口をつく、感覚的な“鳥羽節”を汲み取り、スーシェフとしてサポートするのは、経験豊富な新圖宏之さん。さらに厨房スタッフとして、21歳の金垣友也さんが4ヶ月前に加わった。
(しんしん)(ガッキー)とあだ名で呼び、同世代のシェフとの交流の場へも連れ出し、生産現場を訪れては、作り手たちと直接話す機会を与える。若い2人に自分の持てる経験もネットワークも、すべて共有するのが鳥羽スタイルだ。

ガッキー:僕のような新米の立場だと、シェフと話をすることすら難しいんです、本来は。だけどウチのシェフは技術だけでなく、こうした大切な人との関わり合いまで広げてくれて。
3人の共通の趣味は「服」。音楽も好みが合うらしく、年の差は関係ないようだ。聞いて驚くのは、休みの日でもほとんど3人一緒に行動しているということ。仲のいい先輩後輩のようにして、気になる他店の味を食べに行くにも、新しいコレクションを求めてショップを見て回るのも。それを彼らに言わせると、プライベートと仕事の境がうまいこと連結しているだけ、だそう。
たんに「気が合う」という以上に彼らが何を大切にしているのか、その根底にある意識はこんなやりとりからも。
──どうしたら、そのフラット感って生まれるんでしょう?
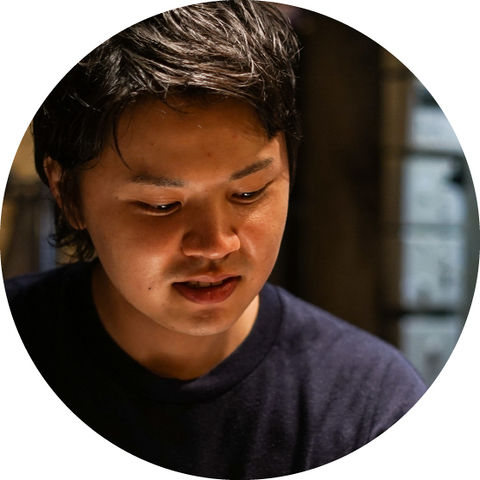
しんしん:あんまりカチッとしたのが好きじゃないんでしょうね。「張り詰めた空気」みたいなのって、ほとんどないですから。仕込みのときとか、よく好きな服の話をガッキーとするんですけど、シェフもそこに乗っかってきちゃうし、むしろ僕らよりもよく知ってて。

鳥羽:基本的に感性が合うってとても重要なんです。「洋服が好き」というのもその一つで、服の趣味や音楽の共有って、結局のところつくり上げるお皿の共有につながるので重要。俺、服好きじゃないとゼッタイ選ばないですからね。面接で聞きますから「洋服好き?」って。調理技術も大事だけど、感性の共有の方が僕らにとっては重要。どんなに有名店で働いた経験があろうと、マジメだったとしても、感性が合わない料理人とはチームになれない。だって、その感性がなかったら、ウチの料理をかっこよくなんて作れない。
調理に限らず、その人に備わる感性のベースがどのレベルにあるか、それを氏は料理以外の側面から判断していた。センスがどこにあるか、そういう感覚値さえ共有していれば、料理を過度に演出する必要はおのずとなくなる。だから、感性の合う人とだけ働く。

厨房、ホールスタッフが毎日一緒になって食べる賄いは、チームとしての結束力を高める大切な時間。もちろん、できたてアツアツには徹底的にこだわっている。
日々の賄いは持ち回り。鳥羽シェフ自ら調理を担当することもある。ホールスタッフも含めた6人全員でできたてをいただく。貴重なコミュニケーションツールであると同時に、クリエイションを生み出す原動力。彼らにとっての「まかない」とはそうした意味を持つもの。

鳥羽:例えば、こないだ酢豚を作ったんですね。あれって脂っこい豚肉がメインで、酸味の利いたソースとしゃくっとした野菜の水分量で中和して、また肉を食べる。こう組み合わせることで、相互のバランスが取れてるからうまいんですよね。
じゃあ、野菜の切り方にどうアプローチするか。それをとことん追求して、日々体現して、実践の場へと活かす。そのための「まかない」だってことです。大したことやってる訳じゃないけど、この積み重ねがGrisの味を作り出していくんですよね。

この日の献立:鶏の照り焼きとポテトサラダ(担当:ガッキー)
切りかたひとつ、盛り付けひとつ、可能性を日々探る。同じ食材と向き合う毎日でも、そこに違いを見出して、柔軟にアプローチを変えていく。この積み重ねが、最終的はまったく違うものとしてアウトプットされる。
「今日より明日のほうがもっと美味しい」と、シェフが力を込めるのは、同じコース料理であっても、2ヶ月のあいだ、一日として同じものは提供しないという、彼らの気概そのものじゃないだろうか。クオリティへの飽くなき追求は、こうやって毎日向き合い続ける人間にしかわからない。
それまで突拍子もないアイデアばかり、ジャブの嵐のように叩きこまれた挙句に、口をついた一言は、ものづくりに従事する人間としての“基本のき”だった。
「昨日作りあげた最高のものをまずは壊すってことが、超重要なんです。それを怖がらないこと。だって、満足したら終わりだから」。

くだんのレストラン「Gris」を支える6人のメンバー。
いま、自分たちが信じる「食」で世界を目指すため、新たなチャレンジの場を広げている。かねてからシェフが掲げてきた「食とストリート」の融合だ。
豪放だが誰よりも繊細な鳥羽周作という人間は、本気であの『Supreme』としらすのコラボを目論んでいる。冗談みたいな話しが、彼の熱弁に気圧されるうち、もしかしたら…の可能性を抱かせてしまうんだから。

鳥羽:俺、別ジャンルの人たちと、これからのクリエイションとか料理とか、そういった未来図を、腰据えてちゃんと話し合わないといけないって思ってて。5年後、10年後に向けて。メディアと食、クリエイションと食、ファッションと食、点と点をどうやって「線」にしていくかが課題だと思ってます。だから、ストリートとスピード感って超重要なんです。料理専門誌なんて、業界の人しか見ないから。もっと別のカタチでいろいろなことをアウトプットしていかないと。
ストリート育ちフレンチの異端児は、見果てぬ夢を追い続ける。
そんな『Gris』への扉はこちらから(予約は忘れずに)。
もう、情報感度の高い人には、きっとこれだけで十分だろう。過度に料理写真を並べられても、シェフのプロフィールを見せられても、店に足を運びテーブルに着いてからの体験は、それらをいっぺんに凌駕するに決まってるのだから。
最高の料理と最高のペアリング、さらに最上級のおもてなしを楽しみに、人生の喜びを知る人たちがGrisには集まってくる。










